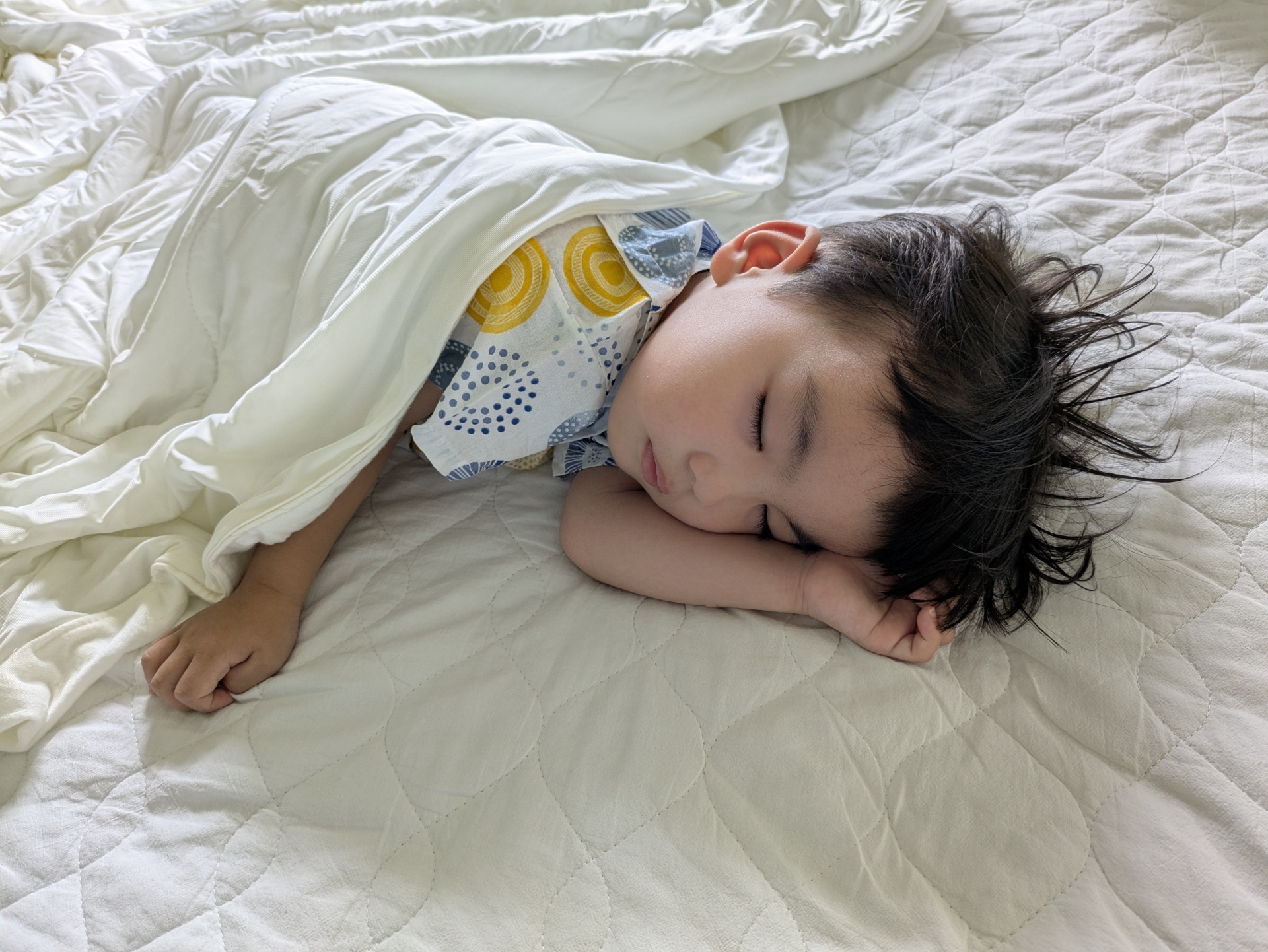
夜──寝る前の工夫
1. 就寝・起床時間を一定に保つ
体内時計(サーカディアンリズム)を安定させるには、毎日の就寝・起床時間の一致が重要です。成人を含む約92,000人のメタ分析では、就寝・起床時刻が不規則なほど健康リスクが高くなる傾向が示されており、逆に規則的な睡眠習慣は健康な体調に寄与すると報告されています。
2. 就寝前の「休息モード」ルーティン
就寝1時間前からスマホなどブルーライトを控え、ストレッチや読書、深呼吸でリラックスすることで、自然な入眠準備が整います。これは睡眠衛生の基本であり、AASM(米国睡眠医療学会)や各種ガイドラインでも推奨されています。
3. 食事・飲料のタイミング
夕食は睡眠2〜3時間前に、カフェインは午後2時まで、アルコールは控えめにするのが理想的。カフェインとアルコールはいずれも睡眠の深さや質を妨げることが多数の研究で確認されています。
4. 入浴習慣を活用する
38〜40℃のお湯に15分ほど浸かると深部体温が上昇し、その後自然に下がる過程で入眠しやすくなります。就寝1〜2時間前の入浴が推奨されているのも、こうした生理学的効果によるものです。
5. 日中のストレス解消
マインドフルネス瞑想、日記、深呼吸などは、心身の緊張を和らげ、入眠をスムーズにします。心理的安定が入眠を後押しする要因として、広く認知されています。
☀️ 朝・日中──活動と光を活かす
6. 朝の光を浴びる
起床後15~60分以内に自然光を浴びると、体内時計がリセットされ、夜自然な眠気が戻ります。24歳前後の学生を対象にした研究では、朝の1000 lxの光を5日間浴びるだけで、睡眠潜時の短縮や夜中の覚醒減少が観察されました。また、20〜81歳の被験者を対象とした11週間の研究では、朝のブルーライト曝露が入眠時間の短縮や深い睡眠の増加に寄与した報告もあります。
7. 日中の適度な運動
ウォーキングや軽いストレッチ、ヨガなどは夜間の熟睡を促進します。ただし、就寝前の激しい運動は交感神経を刺激し逆効果となるため、2~3時間前までに済ませるのが望ましいです。
8. 明るさに配慮する
寝室は暗めが理想ですが、朝や日中は十分な明るさが必要です。対照的に、夜間は照明を落とすことで体内時計への悪影響を防げます。これは光によるメラトニン抑制やPRC(位相応答曲線)の原則から支持されています。
特別な取り組み:光療法(ライトセラピー)
9. 光療法(朝の強光曝露)
2500〜10,000 lxの強い光を朝に一定期間当てることで、メラトニン分泌の位相が前進し、入眠時刻の早期化、睡眠潜時短縮、総睡眠時間の延長などが示されています。代表研究では、慢性不眠患者が光療法により1時間以上早く入眠でき、総睡眠時間が約50分延長されたという報告があります。またシフト勤務者や大学生でも、朝の10~60分強光曝露が翌日の眠気や覚醒効率の改善をもたらしたというエビデンスも多数報告されています。
✅ 総まとめ
-
規則的な睡眠時間+朝の光 → 体内時計を整える
-
適度な運動と環境整備(暗く、快適) → 熟睡しやすい
-
入浴・ストレス軽減習慣 → 自律神経が休息モードに
-
必要に応じ光療法 → 不眠改善や睡眠位相調整に効果的




